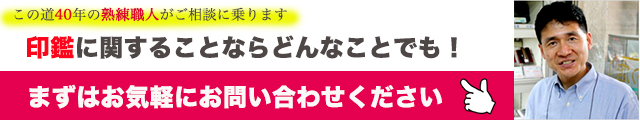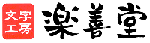東京 八王子 印鑑文字工房 楽善堂の店長が印鑑や文字の魅力を語る
昭和10年代の駅名表示板は右から左へ
朝日新聞 15日(火)のLINE NEWS 、写真を見てびっくりしました。記事の内容は、ローマ字つづりが70年ぶりに変更へ、というタイトルで、この写真で言うと「NISINOMIYA」⇒「NISHINOMIYA」にかわります、というものです。
現在では横書きの表示はほとんどが左から右に読みますが、この駅看板は右から左に「にしのみや」と書いてあります。さらに右下の「甲子園口」のひらがな表記は「かふしゑんぐち」です。「園」のひら仮名は「え」でなくワ行の「ゑ」です。写真の説明は「1939年(昭和14年)頃の国鉄東海道線、西の宮駅の表示板」と出ていました。
当店で接客をしていて、印鑑の配列、横線の画数が多い時(例、後藤さん、齋藤さんなど)のご注文は縦書きでなく、横書きをご提案しています。文字がすっきりと楽に印鑑の中に入るからです。縦書きだとどうしても窮屈になります。特に篆書(てんしょ)体や吉相体の場合です。
右から左に読む例として、店の正面に飾ってある篆額(てんがく)をお客様に示して「この看板のように右から左への横書きが印鑑では伝統手法です。」と説明しています。仕上がってからお客様から「右から読むの、おかしいんじゃないの?」ということのないように、事前のご説明を大切にしています。

「にしのみや」「あしや」にある「し」の文字にある上の一画の点は
ひらがなの「し」の元字が漢字の「之」なので、上にある一画が
ひらがなにも表記されています。料理屋さんの名前表記などに
時折り見かける「し」かと思います。

内藤香石 先生に作っていただきました。